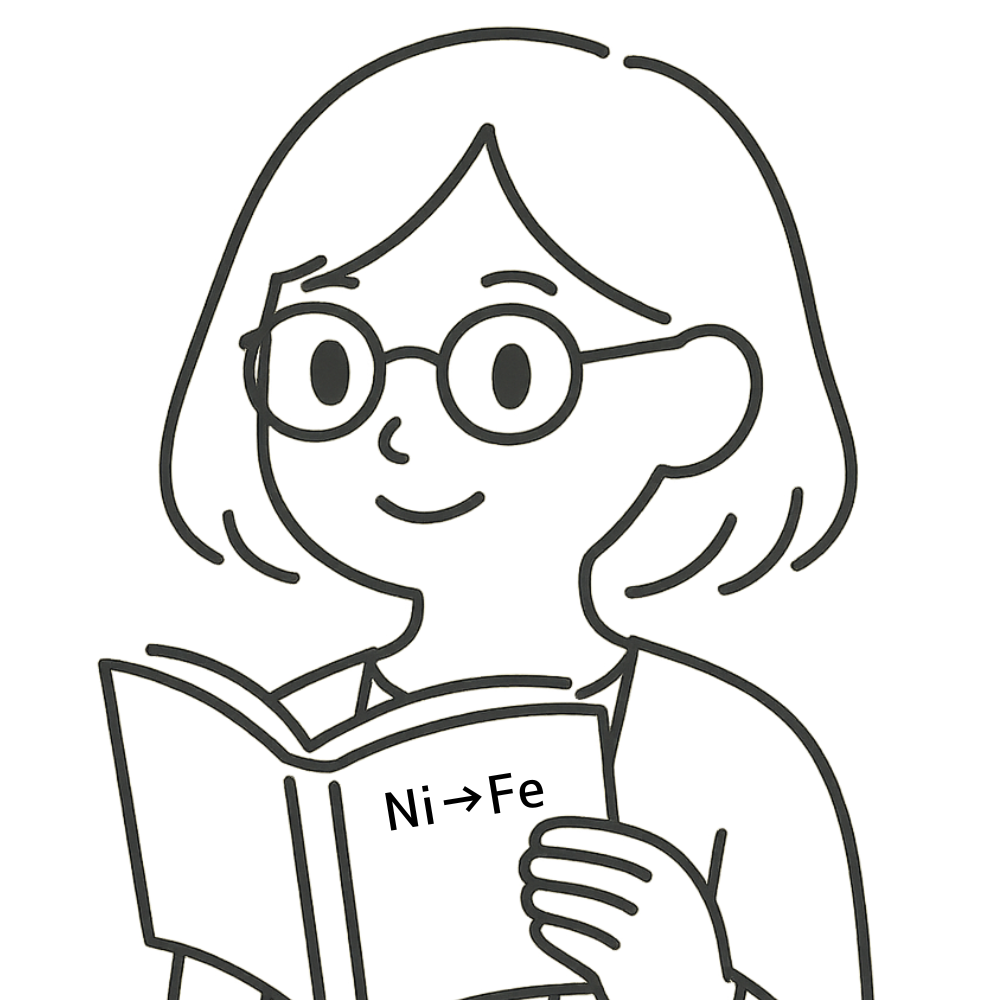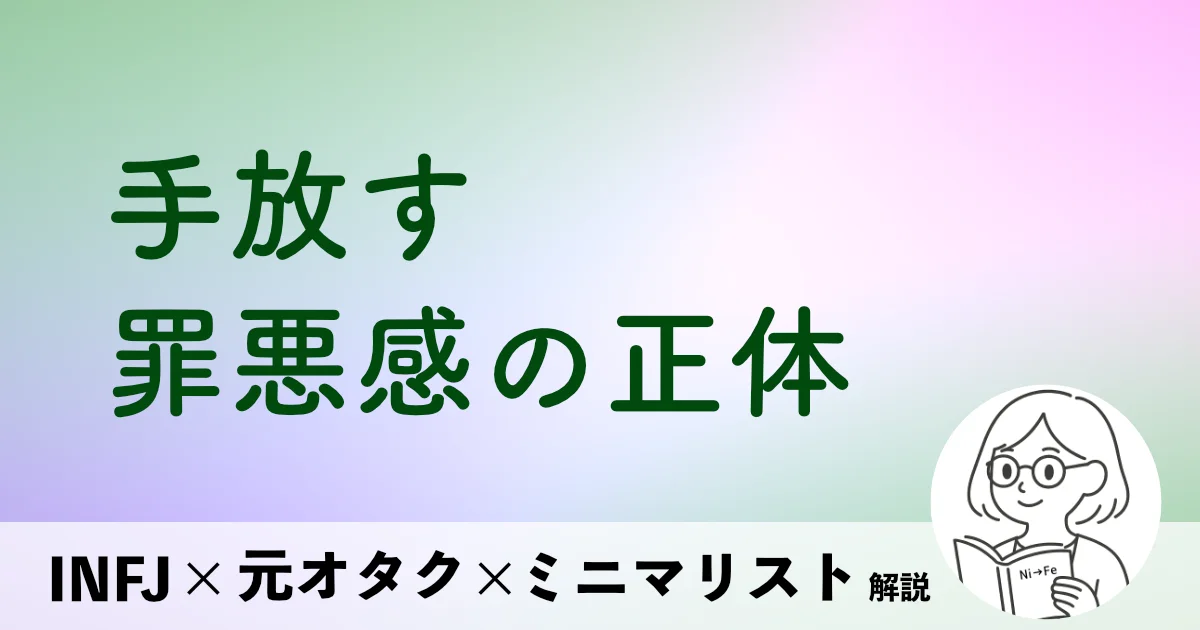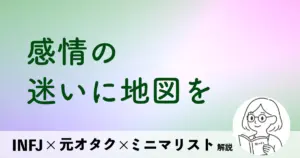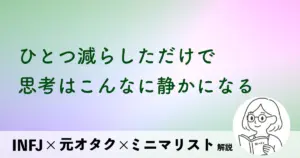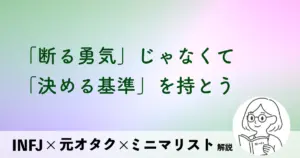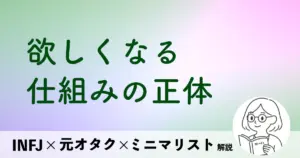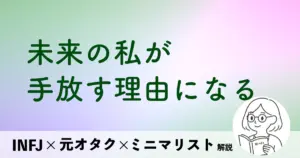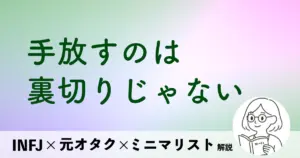「オタクをやめたいけど、やめるのが怖い」
「推しグッズを手放したいのに、罪悪感がある」
そんな葛藤を抱えていませんか?
大好きだった趣味をやめるのは、“自分の一部を失うような痛み”を伴うものです。
特にINFJのように、心のつながりや意味を大切にするタイプにとって、
「好きだった自分を手放す」ことは簡単なことではありません。
私自身、かつてグッズ収集に熱中し、推し活をやめたい気持ちと続けたい気持ちの間で長く揺れていました。
でも、罪悪感と向き合いながら少しずつ整理していく中で、ようやく“心が軽くなる瞬間”にたどり着いたのです。
この記事では、
- オタクをやめたいのにやめられなかった理由
- 推しグッズを整理していく中で見えた罪悪感の正体
- INFJ的に「後悔しないオタ卒」を進める心の整え方
を、私自身の体験をもとにお話しします。
「やめたいのに動けない」そんなあなたが、少しでも前に進めるきっかけになれば嬉しいです。
オタクを卒業したくなった理由
「オタクやめたいけど踏ん切りがつかない」「推しグッズの断捨離を考えている」
そんな迷いを抱えている方は多いのではないでしょうか。
私も長年、推し活にどっぷり浸かりながら、やめたい気持ちと手放せない気持ちの間で揺れ続けていました。
ここでは私がオタク卒業を考え始めた理由と、そのときの心境を振り返ります。
私のオタク活動は主にグッズ集めが中心でした。
ある日、当時ハマっていた「おそ松さん」のコラボイベントで、特設ショップに立ち寄れば十分だったのに「ここでしか手に入らないTシャツがある」と知り、欲に駆られてコラボ先のメインイベントにも参加することにしました。
けれど、やっとの思いで手に入れたTシャツのクオリティは期待外れで、「私、一体何をしているんだろう……」と、イベント帰りの道で強い虚しさを感じたのを覚えています。
推し活は本来楽しいもののはずなのに、気づけば“義務感”や“焦り”に支配されていた自分に気づきました。
オタク断捨離を決めた経緯と心の葛藤
そんな虚しさを感じたあの日から、「グッズ集め自体がいけないのでは」と思い込み、最初はグッズを手放せば楽になれるのではと考えました。
「オタ卒を決めた瞬間に起きた心の変化と、その後の自由」の記事でも語ったように、まずはぬいぐるみ、CD、DVDなど大きく場所を取る物から手放していきました。
でもこのときはまだ「クリアファイルだけは大丈夫」と思っていて、実用性があって、気軽に手に入れられて、収納にも困らないグッズは手元に残していました。
その後、新たにグッズを買うことはなくなり、自然と今まで熱中していたジャンルへの興味も薄れていきました。
次にハマった趣味はスプラトゥーンというゲームでしたが、そのころにはミニマリストとして「本当に必要なもの以外は持たない」という考え方に出会い、一人暮らしを機にクリアファイルなど残っていたグッズもすべて手放しました。
この「身軽な自立を選ぶ」という決断が、私にとって本当の意味でオタク卒業を選択した瞬間だったのです。
「推しグッズを手放すまで|INFJが辿った心のプロセスと学び」で語ったビビのアクションドールは、一度オタ卒を決めた後に出会ったグッズでした。
しかしビビを手に入れた以降も、他のグッズを買い足すことはなく、FFとユニクロのコラボTシャツも2年間使い倒した後に処分し、今では「推しグッズがない生活」を送っています。
(正確に言えば、実用してしまい売りに出せなかったクリアファイルと収納ケース、リュックについているマスコットだけは、今も使用しています。)
アイデンティティの葛藤
私にとって「オタクな自分」は、自分らしさそのものでした。
INFJの私は、一度手放すと完全にリセットしてしまう「ドラスラム」を発動しがちで、グッズオタクをやめる=過去の自分を全否定するように感じたのです。
手放すことで「自分が空っぽになってしまうのでは?」という恐怖もありました。
さらに、ミニマリズムに興味を持ち始めたことで「なんで好きなものだけを追いかけていたのか」と、かつての自分を後悔することもありました。
完全にミニマリズムに走る直前までは、特に金銭面で後悔の連続で、「このままでいいのか」と悩み続けていました。
罪悪感の正体を探る
今振り返ると、オタクをやめる罪悪感の正体は「好きなもの=自分の価値」と思い込んでいたことにありました。
「推しや趣味をやめたら、自分には何も残らないのでは」と不安になっていたのです。
INFJは物事に意味や役割を強く求めるため、「オタクとして生きること」に自分の存在価値を感じていました。
そのため、好きなものを手放す=自分を手放すと錯覚し、罪悪感が生まれていたのだと思います。
やめた後に起きたポジティブな変化
オタクをやめたことで、推しグッズを整理し心の断捨離が進んだ結果、時間とお金にどんな余裕が生まれたのかを具体的にお話しします。
オタク活動を卒業したことで、グッズ情報を追うための情報収集の時間がなくなり、空いた時間で新しい趣味を楽しめるようになりました。
当時はスプラトゥーンに夢中になり、一緒に遊んでくれた人たちに誘われてアモングアス(アモアス)にも挑戦しました。
お金をほとんど使わずに、趣味にたっぷり時間をかけられたのはとても新鮮で、純粋に楽しめた体験でした。
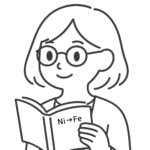 tsumu9
tsumu9詳細はこちらにも書いています↓
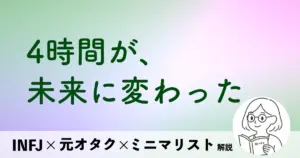
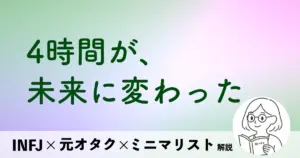
その後「もっとお金を増やしたい」と思うようになり、ゲームから投資の勉強に興味が移りました。
そして投資のためにインデックス投資の入金力を上げようと考えた結果、ゲームも手放しました。
今振り返ると、投資に挑戦できたのも、オタクを卒業して自由に使える時間やお金が増えたおかげだと思います。
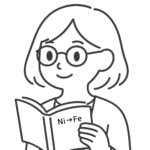
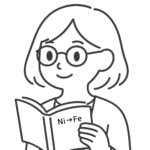
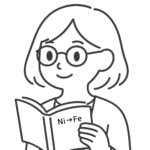
お金の最適化を行いました!
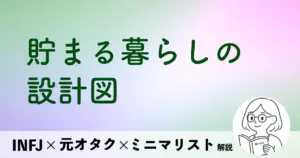
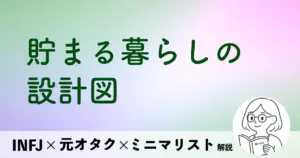
オタ卒後の心の整理の仕方
私自身、グッズを手放すことでゲーマーからインデックス投資家というまったく違う道へ、3年ほどかけて少しずつポジションを変えていきました。
この過程で「あれ、自分って思っていたほどオタクじゃなかったんだ」と気づけたのです。
つまり私は「オタクをやめよう」と決意してやめたのではなく、少しずつ距離を取る中で、気づいたらオタクを卒業していたという感覚に近いものでした。
少しずつ距離を取る大切さ
もし「手放すのが怖い」「自分を失いそうで不安」と感じている人がいるなら、無理に一気に手放そうとしなくて大丈夫です。
少しずつ距離を取りながら、心が追いついたタイミングで手放す方法もあります。
自分のペースで「今の自分に必要かどうか」を考えながら進めていけばいいと思います。
罪悪感を和らげる考え方
やめることは、好きだった自分を否定することではありません。
むしろ「好きだった過去の自分を認め、ありがとうと言って送り出す」ことで次のステージに進めます。
私自身、推し活に夢中だった時間を「無駄だった」と感じることもありましたが、今は「大切な学びや支えをくれた時間だった」と思えます。
好きだった自分に感謝できれば、後悔や罪悪感は少しずつ薄れ、「これから何を大切にして生きたいか」を考えられるようになるはずです。
おわりに
オタクをやめたいけど決めきれない方へ。
推しグッズ整理やオタク断捨離を迷っている方にとって、少しでも心の整理のヒントになれば幸いです。
好きなものを手放すことは、自分を裏切ることではありません。
「好きだった自分を認めて次へ進む」その選択も、自分を大切にする方法の一つです。
自分を責めすぎず、一歩ずつ心を整理していきましょう。
あなたの未来が、より心地よく生きられるものでありますように。
よくある質問(FAQ)
推しグッズを手放したら後悔しますか?
INFJの私自身の体験から言うと、後悔はしませんでした。
未来思考の特性もあり、オタク活動に使ったお金や時間が「無駄だった」とは思わず、学びや経験として自分の成長に変えられたからです。
ただ、Si(内向的感覚)が優勢なタイプの人は、思い出に強く執着する傾向があるため、いきなり手放すと後悔しやすいと思います。
Si優勢の方は、まずはグッズを箱に詰めて封印し、「なくても困らない感覚」を少しずつ確認してから手放すのがおすすめです。
P型の方へのアドバイスは私には難しいですが、手放した先に「こんな未来があるのか」と知ってもらえたら嬉しいです。
オタクを卒業するのは裏切りですか?
私は「自分に素直になれないことこそが、人生における最大の裏切り」だと思っています。
自分の気持ちを押し殺して「オタクであり続けなきゃ」と無理をするより、「好きだった自分を認めて次に進む」選択も大切にしてほしいです。
推しグッズを手放したら推しへの気持ちも薄れますか?
手放したからといって、推しへの気持ち自体がすぐに消えてしまうわけではありません。
むしろ「持ち物として残さなくても、自分の中に推しへの思いや思い出は残る」と感じられるようになることもあります。
大切なのは、物を持つことと気持ちを切り離して考えられるかどうかです。
推し活をやめたら友達との関係はどうなる?
推し活を通じてできた友達がいると、「やめたら関係が終わるのでは」と不安になりますよね。
実際、共通の趣味がなくなることで疎遠になる場合もありますが、逆に「趣味だけの関係だった」と気づけて自分にとって心地いい人間関係を整理する機会にもなります。
仲が良かった友達なら、趣味以外の話題でも繋がっていけるはずです。
推しグッズをどう手放せばいいかわかりません
いきなり捨てる必要はありません。
まずは「箱に詰めて目に入らない場所に置いてみる」、次に「フリマアプリや中古ショップを検討する」、そして「必要なら写真を残して思い出を保管する」など、段階を踏んで進めていくのがおすすめです。
少しずつ心の整理と行動を合わせていければ大丈夫です。