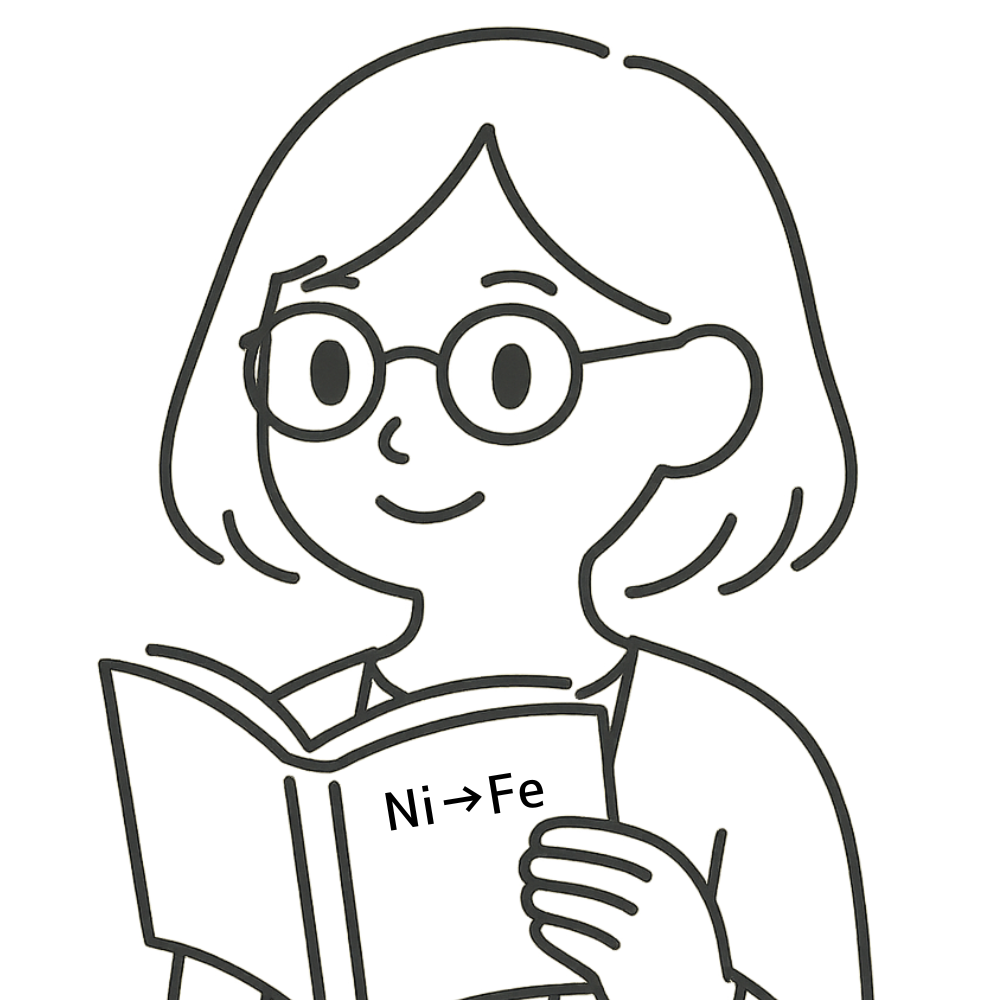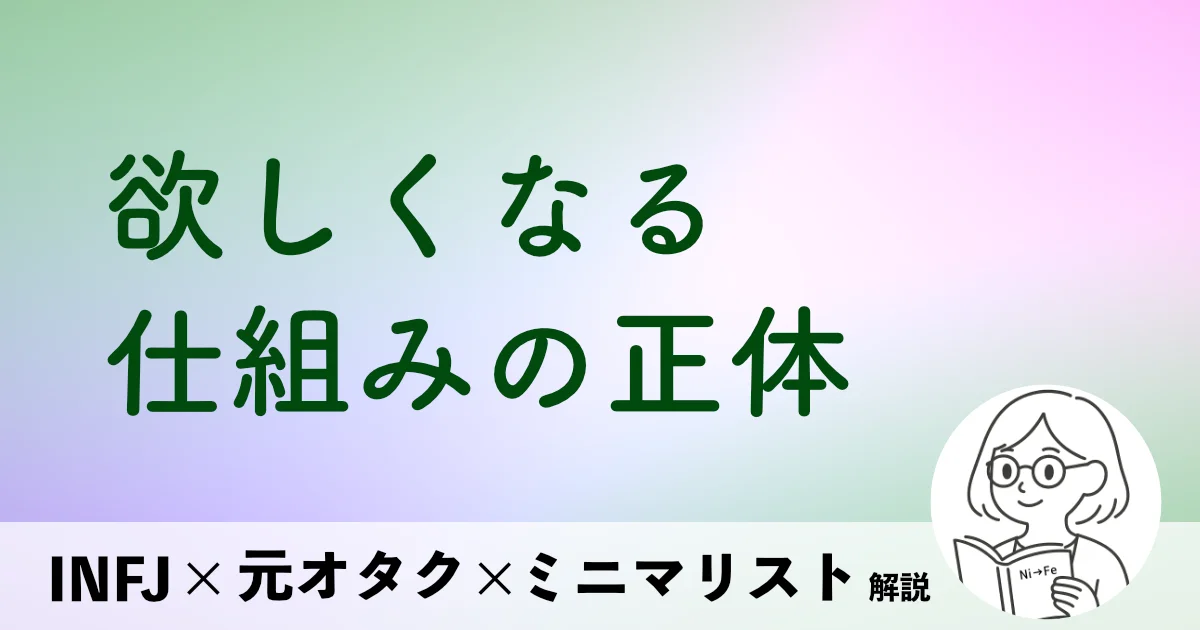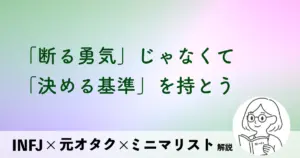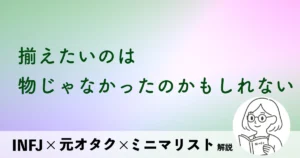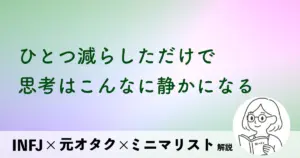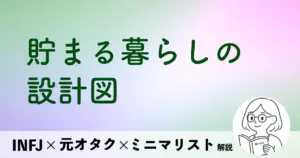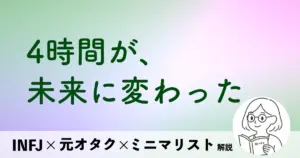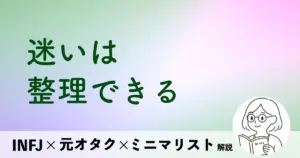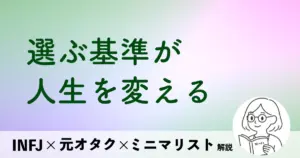「気づけばまた、グッズを買っていた。」
そんな瞬間に、ふと罪悪感を覚えたことはありませんか?
私もかつて、発売日に並び、限定グッズを集めては「もう買わない」と言いながら、また次の新作に手を伸ばしていました。
当時はそれを“意志の弱さ”だと思っていたんです。
でも今は、それがもっと深い心理の仕組みから生まれていたことに気づきました。
私たちはただ“欲しくて買っている”のではなく、
「選ばされている」構造の中にいるのかもしれません。
行動経済学とは、
「人はどのように“非合理的に”選択してしまうのか」を研究する学問です。
合理的な経済理論では説明できない、感情や習慣による購買行動を解き明かす分野でもあります。
この記事では、行動経済学の視点から、
- なぜグッズを集めてしまうのか?
- どうして手放せなくなるのか?
- そして、その仕組みに気づくと何が変わるのか?
を、具体的な心理効果(保有効果・サンクコスト・フレーミング効果など)とともに紐解いていきます。
「もう買わない」と思ってもまた買ってしまう——
その理由を自分を責めずに理解することで、
“選ぶ自由”はきっと、もう一度取り戻せます。
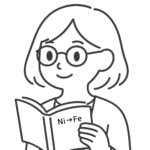 tsumu9
tsumu9それでは、グッズ収集の心理構造を一緒に見ていきましょう。
オタクがグッズを集めたくなる心理とは?
金欠のときには「節約しよう」と思っていたのに、新作グッズの告知が出ると、つい手が伸びてしまう──。
それは決して、あなたの意志が弱いわけではありません。
巧妙なマーケティング手法が、あなたの購買欲をうまく刺激しているのです。
【保有効果】買ったグッズに愛着が湧く理由
たとえば、グッズをひとつ手に入れると「これ、やっぱり手放したくない」「あとで売るなんて考えられない」と感じた経験はありませんか?
この心理は、行動経済学では保有効果(Endowment Effect)と呼ばれています。
人は一度自分の所有物になったものに対して、実際以上の価値を感じる傾向があります。
「持っていないとき」は冷静だったのに、「手にした途端に愛着が湧いて手放せなくなる」──それが、保有効果です。
つまり、「一度買ったグッズを手放せない」のも、「初めて手に入れたグッズの感動が忘れられず次も欲しくなる」のも、心理的にはとても自然なことなのです。
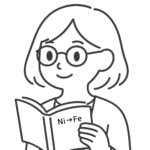
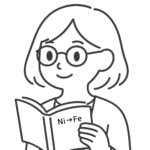
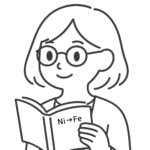
今思うと私もこれにハマっていたから、グッズ集めしていたんでしょうね…
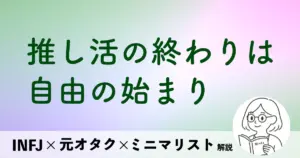
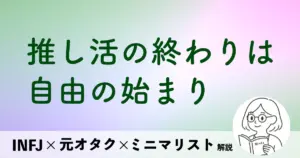
【ツァイガルニク効果】あと1個…が止まらない心理
ガチャガチャやくじ形式のグッズで、「あと1個で揃う」と分かった瞬間、冷静さが吹き飛ぶ…そんな経験はありませんか?
この現象はツァイガルニク効果と呼ばれ、「人は未完了のことを強く意識し続ける」という心理から来ています。
「コンプしたい…!」という衝動は、この“未完のストレス”を解消したいという自然な欲求なのです。
【フレーミング効果】「限定」に弱いのはなぜ?
「○○限定グッズ、数量わずか!」「本日23:59までの受注生産!」
──そんな言葉を見た瞬間、財布のヒモが緩んだ経験はありませんか?
実はこれ、あなたの“意志の弱さ”のせいではありません。
これはフレーミング効果(Framing Effect)と呼ばれる心理現象で、情報の“見せ方”によって感じ方や判断が変わるというものです。
たとえば、「このグッズは5,000円」と言われるよりも、
「今買わないと二度と手に入りません」「在庫あと3個です」と言われたほうが、焦りが生まれやすくなります。
オタク活動では、“限定”や“残りわずか”という言葉のフレームが、商品そのものの価値よりも、今しかない機会を強調してきます。
これによって、
- 使う予定のないグッズなのに買ってしまった
- セットの中の一部だけが欲しいのに全種類購入してしまった
といった経験が起きやすくなるのです。
つまり、“限定”に弱いのもまた、人間の自然な認知のクセ。
まずはそれに気づくことが、モノとの距離感を見直す第一歩になります。
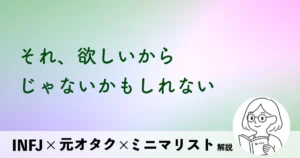
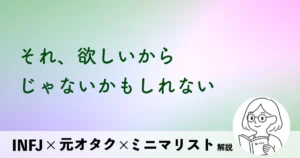
なぜグッズが手放せないのか?──サンクコストの心理
物が増えたら、古いグッズは手放してもいいのでは?と客観的にも思うことはあっても、なかなか手放すのは難しいですよね。
実はこれも、行動経済学の視点で説明できます。
【サンクコスト効果】過去の努力が執着に変わる
「もう飾っていないし、正直ちょっと場所をとる…」
そう思っても、いざ手放すとなると、なんだか惜しくなってくる。
特に、たくさん集めたシリーズ物や、お金や労力をかけて揃えたコレクションほど、その傾向は強くなります。
これはサンクコスト効果(Sunk Cost Effect)と呼ばれる心理現象です。
「すでに払ってしまったお金や時間を“ムダにしたくない”」という気持ちから、合理的な判断ができなくなってしまいます。
たとえば、
- 推しのライブグッズをコンプリートしたから崩したくない
- 徹夜で並んで買った限定グッズだから、手放すのがもったいない
- 高かったから売っても安くなるのが悔しい
──こうした感情は、過去にかけた「コストへの執着」が現在の選択を縛ってしまっている状態です。
でも、サンクコストはもう取り戻せない過去の投資です。
「これからの自分にとって、そのモノは本当に必要か?」という未来基準で考えることで、気持ちを整理しやすくなります。
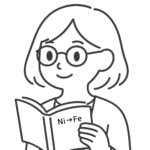
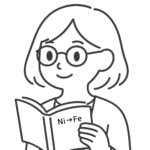
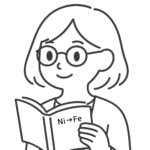
執着の正体がわかったら、次はそのモノが自分の心の中でどの『理由』に分類されるかを確認してみてください。
12の分類に当てはめるだけで、手放す心の準備が整います。
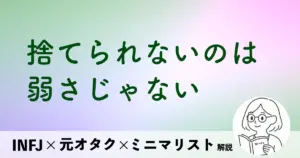
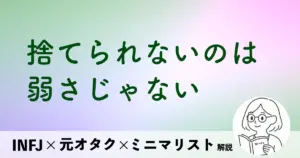
【確証バイアス】思い出がグッズを手放せなくする
あのグッズは、推しの誕生日に仲間と盛り上がった日を思い出させてくれる。
だから、もう使ってないのに捨てられない…。
これは“感情的な付加価値”や“記憶のピーク”によって、そのモノが「ただの物」ではなく「過去の幸福体験の象徴」になっているからです。
さらに影響しているのが、確証バイアス(Confirmation Bias)です。
これは、「自分の選択は正しかった」と思いたい気持ちが、ポジティブな記憶ばかりを集めてくる現象です。
「このグッズを買ったのは、あの楽しかった時間の証」
「大切にしてきたから、今も手放せない」
──そうやって、過去の選択を正当化する材料として“思い出”を強調しがちになるのです。
でも、こう問い直してもいいのかもしれません。
「その思い出を大切に思う気持ちと、今の暮らしを見つめ直すことは、両立できるんじゃないか?」と。
【確証バイアス】思い出がグッズを手放せなくする
SNS投稿がグッズ集めを加速させる理由
「届いた〜!」「○○ちゃんお迎え♡」
そんな投稿でタイムラインが彩られるたび、心がそわそわしたことはありませんか?
私もかつて、推し活用のアカウントで、グッズを並べては写真を撮り、SNSに投稿していました。
「自分も持っているよ」とアピールすることで、“推しへの愛”を証明したかったのだと思います。
これは、社会的証明(Social Proof)という心理が働いている状態です。
「みんながやっているなら、それが正しい/価値があるはずだ」と判断してしまう、無意識のバイアスです。
さらに、SNSという場では「いいね」やコメントという数字が、私たちの“自信”や“承認”の物差しになっていきます。
それはいつの間にか、「人に見せるためのグッズ集め」になっていたことにも気づかせてくれました。
私はなぜ“見せるために集めていた”のか
最初は、好きな作品のグッズを持てたらいいなという純粋な気持ちで買っていました。
ところがSNSを見て、世の中にはたくさんグッズを持っている人がいることを知ります。
外は外、うちはうち──そう思っていたつもりが、いつの間にか比較の波に飲まれていました。
ある日、イベント帰りの電車で、ふと「私、今なにしてるんだろう…」と冷静になった瞬間。
そのとき、「私は“見せること”が目的になっていたんだ」と、ようやく気づいたのです。
気づいた私は、中古ショップにまとめて買取依頼をして、2回に分けて手放していきました。
オタクの購買行動は「設計された心理」だった?
グッズを買う=オタクの証明
グッズを持つ=“愛”の深さの証明
グッズをSNSで共有する=“熱量”の証明
こうした価値観は、実はすべて“企業が設計したもの”である可能性があります。
商品に「意味づけ」がされることで、私たちは“買う理由”を与えられ、行動を誘導されているのです。
その衝動は“戦略的に作られていた”
グッズを買ってしまった自分は、意志が弱かったわけではありません。
オタクのグッズ集めには、複数の心理が複雑に絡み合っている。
つまり、購入することを“選ばされている”状態だったとも言えるのです。
心理に気づけば、「選ぶ自由」が戻ってくる
こうした心理的な仕組みに気づくことで、
「これは本当に自分が欲しいものなのか?」
という視点で、冷静に選べるようになります。
自分の選択が間違っていたわけじゃない。
ただ、私たちは思った以上に「巧みに誘導された状況」にいた。
だからこそ、「次にどう選ぶか」は、もう一度、私たちの手に戻ってくる。
それは、意志の強さではなく、“仕組みに気づいた人の特権”かもしれません。
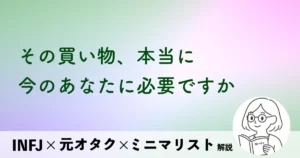
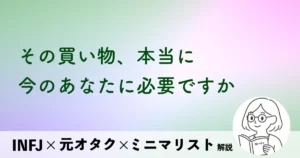
おわりに
私たちがグッズを集めてしまうのは、意志が弱いからでも、欲深いからでもありません。
人間という生き物がもつ“非合理な心理”が、日常の中で自然に働いているだけなのです。
行動経済学は、そんな人の非合理さを否定せずに理解する学問です。
「なぜこんな選択をしてしまうのか」を責めるのではなく、
「どういう仕組みでそうなっているのか」を見つめ直すためのレンズ。
つまり、気づくことで「もう同じ後悔を繰り返さないようにしよう」と、
自分を優しく再設計できるようになる学びなのです。
グッズを買うことは、あなたの“好き”を形にした行動でした。
そこに込められた想いや喜びは、決して無駄ではありません。
でも、その心理の構造を知った今なら、
「これは本当に必要かな?」と立ち止まれる“選択の余白”を持てるはずです。
行動経済学の本質は、人を変えることではなく、人を理解すること。
だからこそ、「買ってしまった自分」を責める必要はありません。
大切なのは、“仕組みに気づいたあとの選択”。
その選択が、これからのあなたの暮らしを、もっと自由で心地よいものに変えていくはずです。